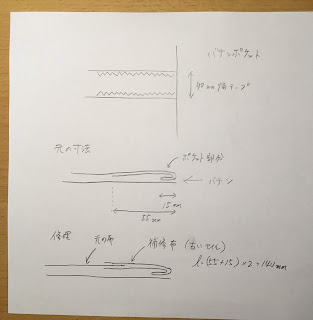Windows環境、Wordで論文を書き、PowerPointでプレゼンをする。数式をどうやって入力するのかが課題であった。Wordの2000年初頭までは附属の数式エディタでそこそこ軽快に数式入力をしたり、フォントを整えたりできたと思うが、今のWord2019環境では、デフォルトのフォントも変わり、さらに、フォント変更が一手間必要だったりとにかく思い通りに動いてくれない。Officeの最新版ではTeX入力もできるという情報もあったがよくわからないまま今に至っている。
特に今年からオンライン授業を行ったことをきっかけに、授業形態を板書からスライドへ大きく移行することになり、数式を大量に扱う必要が出てきたことが、それ以前との相違点である。
Windows環境の傍ら、今年から iPad Pro + ApplePencil2 も使うようになってきたので、それも含めて何か良い方法を確立したかった。要求性能をまとめると以下の通り。
- 数式の再利用(再利用しての修正)ができること。
- 最終的に、WindowsのOfficeへメタファイル等で入れることができること(背景が透過であれば、ファイル形式は他でも良い)
- 方法は、Windowsのアプリ、iPad+ApplePencil、ウェブサービスのどれでも良いが、永続性のあるもの。
色々探してみたが、結局落ち着いたのが、TeX環境であり、 pptTeX という、TeX環境をパワーポイント上から利用できるツールである。
インストールに関しては、著者のサイト(http://naitaku.github.io/pptTeX/)に書いてある通り実行すればよいのだが、最低限のことしか書かれていない。パラメーターなどは、他のサイト(例えば、https://qiita.com/kzkadc/items/7c32d1633e7093461128)を参考にすればよい。
ただし、うまくいかなかった。インストールがうまくいっていないのか、環境設定が悪いのか、OSの64bitとアプリの32bit環境の混在なのか、よくわからなかった。原因究明に2日間(2020/12/20~2020/12/28)、計6時間ぐらい費やしたと思うが、結果としてはこちらのサイトに書かれている通り(https://armik.hatenablog.jp/entry/2020/06/16/213026)、GhostScriptのバージョンが新しすぎたためであった。
不具合の内容としては、パワーポイントに挿入された画像には、「×この画像は表示できません。」と書かれた枠だけが挿入されていた。作業フォルダを見ると、本来挿入されるべき
tmp.emf ファイルが空(0kB)で、
tmp.eps ファイルは無事作成されていた(pdfに変換すると、数式はできている)。
最後のepsファイルをemfファイルに変換することができていないようだった。
ということで、上記の通り、先人によって動作確認されている 古いバージョンのGhostscript 9.26をインストールしなおして、動かすことができた。32bitか64bitかについては、Windows10は64bit、Ghostscript他必要なインストールは、32bit環境とした(試行錯誤しているときには、色々変えたりしていたが、今回先に32bitで動いたのでそれでストップしただけ)。
環境設定は次の通り、
C:\texlive\2020\bin\win32\platex.exe
C:\texlive\2020\bin\win32\dvips.exe
C:\Program Files (x86)\pstoedit\pstoedit.exe
C:\Users\xxxxx\AppData\Local\Temp\pptTeX
xxxxxは自分のログオン名
インストールに際しては、(途中うまくいかなかったときに)TeXインストーラ3(W32TeX環境)なども試してみたが(消していない)、結局上記の通り単体でインストールして、環境設定をしている。
成果は次の通り。
とりあえずは、Wordで使用する場合には、PowerPointで数式を作り、その画像をWordへコピーして使うこととする。- TrueTypeフォントとすると拡大しても綺麗なのだが、パワーポイントファイルを配布したとしたら先方で数式フォントがないと文字化けやレイアウトがずれることがわかった。よって、パワーポイント貼付に関しては、Outline(画像化)で対応するのが無難である。
- Outline化していても、再編集ができるのが素晴らしい。
- 数式フォントも多数フリーのものがあり、変更できるようであるが、まだよくわかっていない。
- 日本語の混在は不可。パワーポイント内に画像として数式を挿入する使い方なので、日本語と分けることで対応ができるのでその点は問題ない(~である、という風に少し日本語を交ぜたいときに面倒であるが、致命的な欠点ではない)。ただ、専門分野で頻繁に使用する記号は単語登録しておき瞬時に出せればと思ったが、使用するエディタ内では日本語入力が不可になっており、その変換入力ができないことが少し残念。ただしこの指摘は、ソフトの使用を諦めるほどのデメリットではない。
- 同業他社ソフトとしては、IguanaTeXというのがあり、最近のバージョンでは日本語も扱えるという情報を得た。ただし、情報が少ない(情報が多いのが、日本語にネイティブで対応する以前のカスタマイズ情報等)のでよくわからない。今後の課題とする。